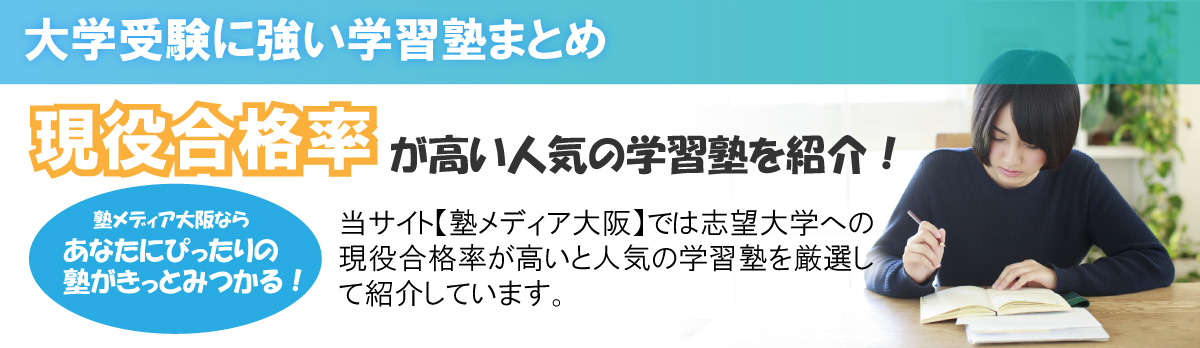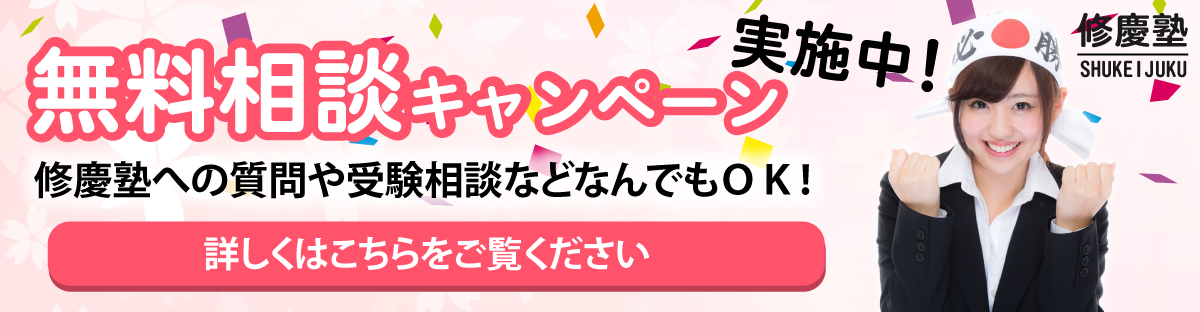私は「ガリ勉」だった。
昔の自分を表現すると、どうしてもこの言葉になる。
何しろ私は、細かいことがいちいち気になり、暗記用の単語カードを自作する子どもだった。
40年近くたったいまでも、努力家で、勉強の虫で、働きバチだったこの少年が、安物のデスクランプの明かりに目を細めながら、
教科書にかじりついている姿をはっきり思い浮かべることができる。
この少年は朝も早く、5時には勉強を始めていた。
高校2年生になって習得できないことが出てくると、胃に不快感を覚えるようになった。
二次方程式の解の公式、アメリカがルイジアナを買収したときの条件、武器貸与法、平均値の定理、
詩人のT・S・エリオットが隠喩を用いて皮肉を表す用法…。
こんなのは序の口だ。
私は学校の授業にすっかりついていけなくなった。
だから、不安しかなかった。時間が足りないのに覚えることは多すぎて、なかにはとても理解できそうにないこともある。
そういえば、不安とは別に自分を疑う気持ちもあった。ただしこちらは、階下の風呂場でしたたる水滴と同じで、自覚するのに時間がかかる。
たとえば、運動能力の高い同級生が汗一つかかずに山小屋へたどり着くのを見たとき、
私はルートを間違えて遠回りしたのではないかと自分で自分を疑った。
私はご多分にもれず、学習は自己の鍛錬がすべてだと信じて大きくなった。
賢い人々が暮らす、知識という険しい岩山をひとり孤独に登るつらい作業、それが学習だ。
私の場合は、好奇心や疑問からというよりも、その山から落ちるのが怖くて勉強していた。
そうした不安から、変わり者の生徒が誕生した。
勉強に自信が持てない時代

弟や妹にとってはミスター・パーフェクトで、ほぼAをとる真面目な兄だった。
だが、クラスメイトにとっての私は透明人間だった。
自分の理解に自信がなさすぎて、ほとんど発言しなかったのだ。
こうした二面性を持つようになったからといって、当時の私、両親、教師の誰のことも責めるつもりはない。
どうして責められるだろう?学習にある程度没頭できるようになる方法と言えば、ソリ犬のごとく自らを駆り立てること以外に誰も知らなかった。
勉強で成功するためにもっとも重要なのは努力だと、誰もが思っていた。
だが、私はすでに努力していた。もっと違う何かが必要だった。そして、その何かはきっとあると感じていた。
最初のヒントとなったのは同級生の態度だった。
私のクラスには、代数や歴史の授業で追い詰められた顔になることなく実力を最大限に発揮できる生徒が数人いた。
その場ですべてを理解しなくてもよいというお墨付きをもらっているかのように振る舞い、
彼らが疑問を口にすると、それ自体が貴重な武器に思えた。
だが、私にとって本当の転機となったのは大学入試だった。私が勉強してきたのは、もちろん、 大学に入るという使命のためだ。
だが、その使命は果たせなかった。
何十という願書を送ったが、見事に閉めだされた。
何年にもわたって水夫のような苦労を積み重ねたというのに、最後に残ったのは、一握りの薄い封筒と補欠合格の1枠だけだった。
その大学に入ったものの、1年で退学した。