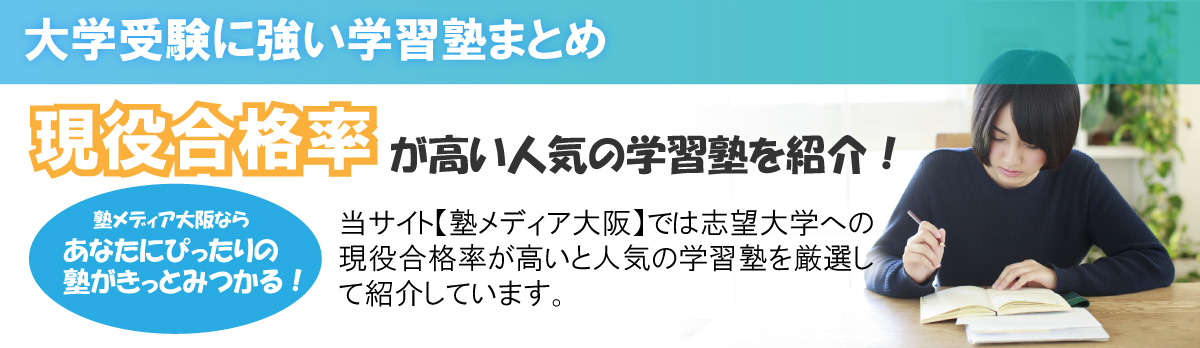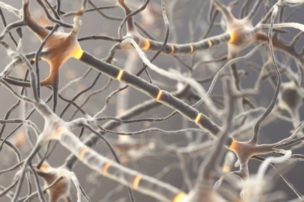いまでもはっきりと脳裏に浮かぶ
今では大学受験の塾講師をしている私も高校生の時はあった。
私は1974年9月に高校生活の初日を迎えた。
いまでも、1限目の鐘が鳴ったときに廊下 で話しかけた教師の顔を覚えている。
私は自分の教室がどこかわからず、人がいっばいの廊下に立ちすくみ、遅れたらどうしよう、何か大事なことを聞き逃したらどうしようと不安に思っていた。
そこに差し込んでいたくすんだ朝の光、汚れた茶色っぽい壁、ロッカーにタバコの箱を投げ入れていた上級生が、いまでもはっきりと脳裏に浮かぶ。私は廊下にいた教師に近づいて「すみません」と声をかけた。
その声は、思っていたよりも大きくなった。
教師は立ち止まり、私が持っていた時間割に目を落とした。
優しそうな顔に細いメタルフレームのメガネをかけた、赤毛が柔らかそうな男性だ。
「ついてきなさい」と笑顔まじりに教師は言った。
「君は私のクラスだ」助かった。
このときのことを思いだしたのは35年ぶりだったが、このとおりちゃんと覚えている。
それも、漠然とではなく具体的に思いだすことができ、長く考えるほど、細部がどんどんよみがえってくる。
リュックから時間割を取りだそうとしたときに肩からリュックが滑り落ちた感覚や、教師と並んで歩きたくなくて足取りが重かったこともよみがえった。
私は数歩離れて教師の後ろをついていった。
この種のタイムトラベルのことを、科学の世界では「エピソード記憶」または「自伝的記憶」と呼ぶ。
そう呼ばれるにはちゃんとした理由がある。
その記憶には、オリジナルの体験のときと同じ感覚、同じストーリー構成が含まれているのだ。
オハイオ州の州都や友人の電話番号を思いだすときは、それを覚えた日時や場所はよみがえってこない。
この種の記憶は「意味記憶」と呼ばれる。
それを記憶したときのストーリーには関係しないが、記憶している内容と関連性のある場面でその記憶がよみがえる。
たとえば、オハイオ州の州都であるコロンバスと聞くと、その地を訪れたときの風景や、コロンバスに引っ越した友人の顔、オハイオが答えのなぞなぞなどが思い浮かぶだろう。
これらは知識としての記憶であって、出来事に関する記憶ではない。
とはいえ、脳が記憶から「コロンバス」を引きだしたという記憶という意味では同じだ。
脳は好奇心が詰まった宇宙のようなものだ。
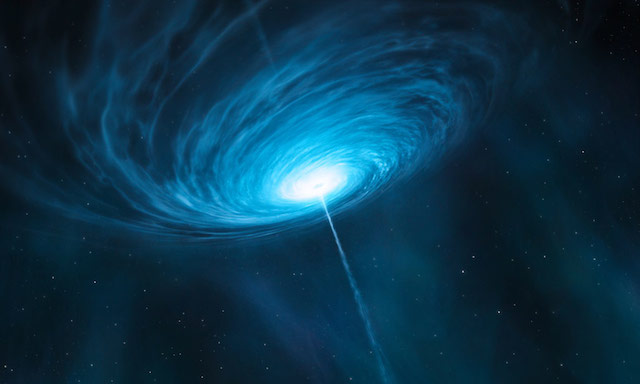
そこにはきっと、記憶の一覧表のようなものがあるのだと思う。
ブックマークの役割を果たす分子があって、それがいつでもニューロンのネットワークへのアクセスを可能にし、自分の過去、自分のアイデンティティを与えてくれるのだろう。
このブックマークがどのように機能するかはまだ明らかになっていないが、コンピュータの画面上に貼るリンクと異なることは確かだ。
ニューロンがつくるネットワークは流動的なので、いま私が思いだす記憶は、1974年当時にできた記憶とはかけ離れている。
詳細さや鮮明さが失われているし、昔を振り返るのだから、少々、いや、かなりの編集が加わっていると思う。
言ってみれば、中学2年生のサマーキャンプから帰った翌朝、キャンプで恐ろしい思いをした出来事について書き記し
その6年後、大学で改めてその出来事について書くようなものだ。
6年後の作文は最初のものとはかなり変わる。
作文を書く自分自身も、自分の脳も6年前とは変わっている。
それが生物学的にどんな変化をもたらしたかは謎に包まれているが、6年間の体験が影響を与えているのは間違いない。
とはいえ、出来事自体(ストーリーの大筋)は基本的にきちんと思いだすことができる。
このことから、専門家たちには、その記憶がどこに保存されているのか、なぜそこに保存されるのかの見当がついている。
しかもそれは、なぜか安心感を覚える場所だ。
高校生活初日の記憶が頭のてっぺんにあるような気がするなら、何とも素敵な言葉の一致だ。
まさにそう表現できる場所に保存されている。